第1回:“〇〇さんに聞かないと分からない”状態を放置していませんか?
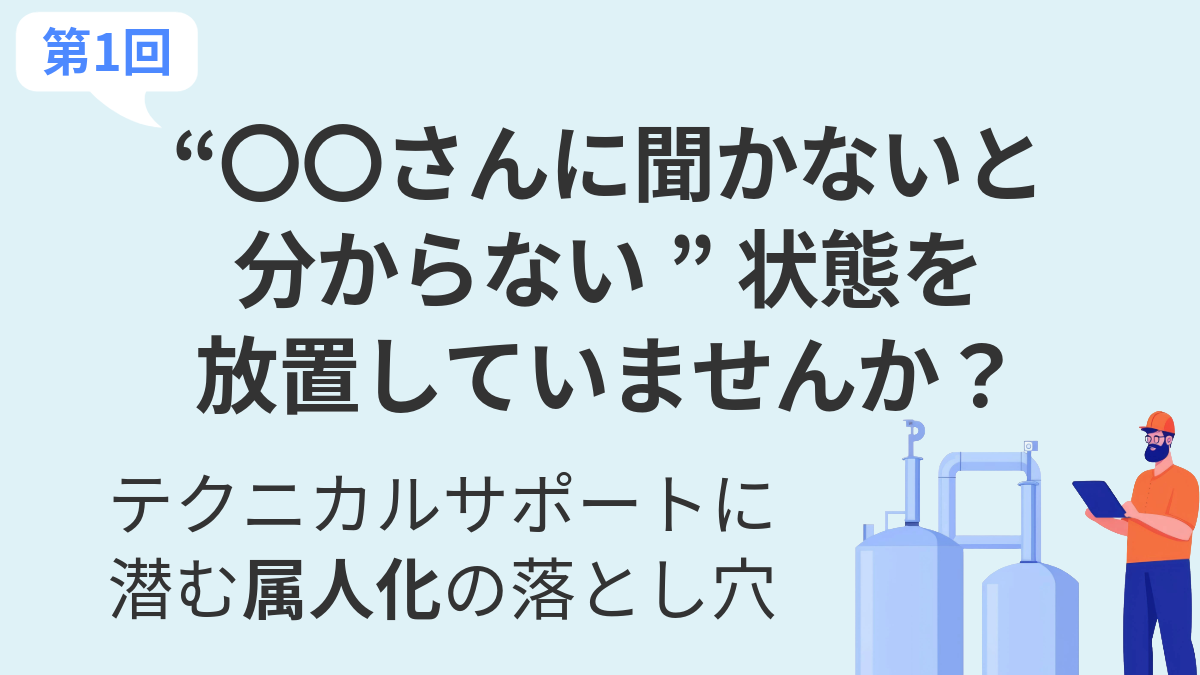
「前任者に聞いてください」で止まる現場
「このシステムの仕様、どこにまとまっている?」
「保守手順書が見当たらない…」
「当時の担当者が退職していて、詳細が分からない」
そんなやり取り、テクニカルサポートの現場で日常的に起きていませんか?
装置やシステムの導入から数年が経過すると、担当者が異動・昇進・退職してしまい、知識や対応履歴の引き継ぎが不完全なまま、業務が継続されるケースが増えてきます。しかも、それが「当たり前」になってしまっている企業も少なくありません。
実際、製造業やIT機器ベンダーなど、お客様ごとに個別対応が必要な「一品もの」の提供を行っている企業では、その傾向が顕著です。属人化は、単に業務のやりにくさという問題にとどまりません。対応品質の低下や顧客満足度の低下、さらには新しいビジネスチャンスの損失へとつながる、極めて深刻な課題なのです。
属人化が引き起こす3つの問題
属人化とは、ある業務や知識が特定の個人に依存している状態を指します。そして、それがテクニカルサポートの分野で発生すると、次のような問題を引き起こします。
① ナレッジが担当者の頭の中にしかない
「その対応は〇〇さんに聞かないと分からない」
「あのときの特殊対応は、本人にしか分からない」
このような状態では、誰かが欠勤したり、退職したりするだけで、業務が止まってしまいます。つまり、ナレッジが“組織の資産”ではなく、“個人の所有物”になってしまっているのです。
② 新人が育たない・即戦力化しにくい
ベテラン社員の経験値に頼り切っていると、新人は常に「教えてもらう側」になりがちです。結果として、自発的に学べる仕組みや資料が整っておらず、育成コストが膨らむ一方、現場の即戦力化も遅れてしまいます。
③ 過去の情報が埋もれ、トラブル対応が遅れる
仕様書・設計書・メールなどが散在し、必要な情報を探すだけで30分以上かかる…。その間にお客様からは何度も催促が入り、信頼はじわじわと損なわれていきます。
属人化は“自然発生”する
ここで重要なのは、「属人化は放置した結果ではなく、自然に発生してしまう構造的な問題である」という認識です。
テクニカルサポート業務の特性上、属人化は次のような理由で起きやすい傾向があります。
理由①:ナレッジの更新が業務に追いつかない
装置やシステムは導入後も細かな改善や改修が続きますが、それに応じてマニュアルや手順書を更新する時間が取れない現場も多いはず。結果として、過去の情報が更新されず、現場で共有されないまま放置されていきます。
理由②:情報がバラバラに散在している
ファイルサーバー、メール、個人PC、チャット…ナレッジが保存される場所が複数にまたがり、統一的に管理されていないことも属人化の温床です。「どこかにあるはずだけど、探し出せない」という状態が常態化してしまいます。
理由③:共有よりも“今の対応”が優先される
トラブル対応が日常的な業務である以上、「とりあえず自分でやった方が早い」という判断が優先され、ドキュメントの整備やナレッジ共有が後回しになります。
属人化の放置は“成長阻害”に直結する
属人化は、現場の手間やトラブル対応の遅延だけでなく、企業全体の成長を阻害する重大なリスクにもなります。
● 顧客対応の品質が不安定に → クレーム増加や信頼低下
● 業務引継ぎが属人的に → 担当者の交代時にパフォーマンス低下
● 改善提案やイノベーションの停滞 → 過去の履歴を活かせず、同じ失敗を繰り返す
これらは、すぐに数字に表れない「見えにくいコスト」ですが、確実に企業活動にダメージを与えます。
次回予告:では、どう脱属人化する?
では、こうした属人化の構造からどう抜け出せばよいのか?
手始めにできるのは、
● 過去のナレッジを集める
● 検索しやすくする
● 教える仕組みを整える
といった、3つの第一歩です。
次回のブログでは、この「脱属人化の3ステップ」について、具体的な方法を解説します。AIを活用することで、今の業務を止めずにナレッジを“生かす”仕組みを整える方法をご紹介します。
あなたの現場にも、属人化の種は潜んでいます
「属人化しているのは分かっているけど、今は手が回らない」
「いつか何とかしたいが、日々の業務に追われている」
そんな声を私たちは多く耳にします。しかし、だからこそ、小さな第一歩から始めることが、将来の大きな改善につながるのです。
次回もぜひご期待ください。
第2回:属人化から脱却するための3つのポイント
属人化を解消するための実践ガイドは以下よりダウンロードいただけます。
