第2回:属人化から脱却するための3つのポイント
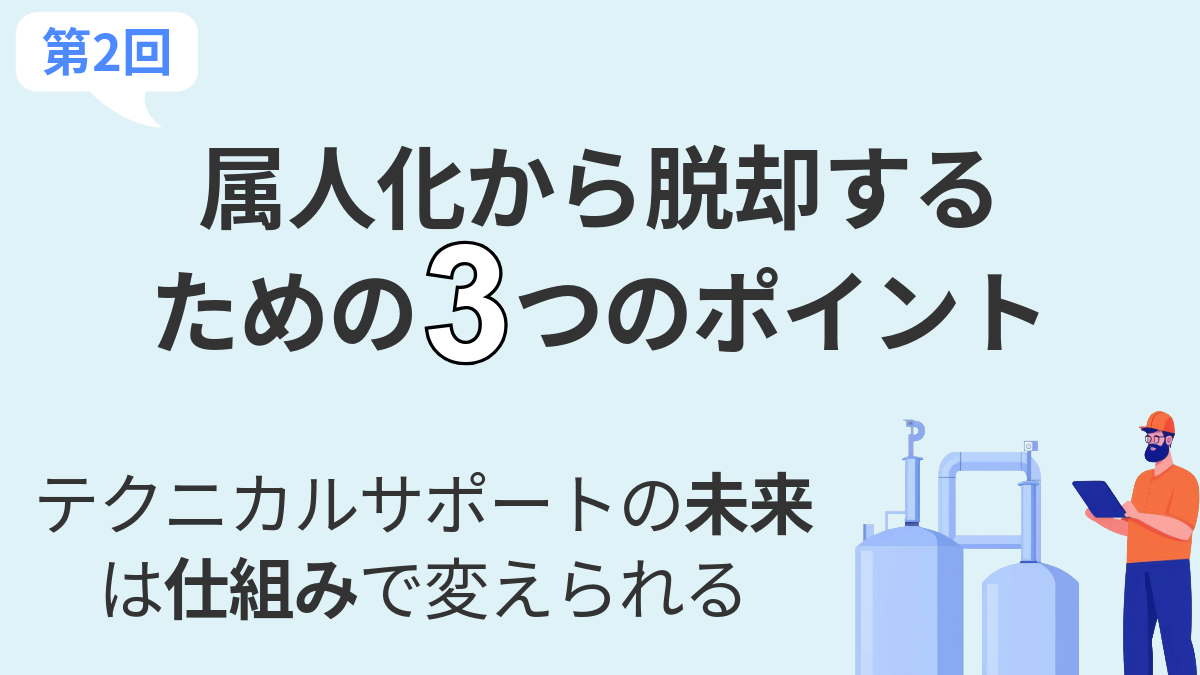
属人化の構造は“偶然”ではない
前回の記事では、「〇〇さんに聞かないとわからない状態」を放置することが、テクニカルサポート現場の大きなリスクになることをお伝えしました。
そしてその背景には、「ナレッジが個人に依存しやすい構造」があることも見えてきました。
つまり、属人化は偶発的に起きるものではなく、現場の仕組みの“穴”に起因する必然的な現象なのです。
だからこそ、脱属人化に向けては「仕組みの立て直し」こそがカギになります。
今回は、明日からでも始められる属人化から脱却するための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①:業務フローの「標準化」と「可視化」
属人化した現場の多くでは、業務の進め方が人によって異なり、「なんとなく」動いてしまっている状態が見られます。つまり、誰が・どの順番で・どんな判断をしているのかが、他の人からは見えないということです。
こうした状態では、ミスやムラが発生するだけでなく、新人がどこから学んでよいのかも分からず、育成も困難になります。
取り組み例:
● サポート業務の流れを「対応フロー図」で可視化する
● 対応カテゴリ(例:製品別・問い合わせ別)の標準対応手順を用意する
● よくある事例や判断ポイントを「TIPS集」として蓄積する
ポイントは、完全なマニュアルを一気に作ることを目指さないことです。まずはよくあるパターンから。小さな整備でも、可視化された業務は“共有可能なナレッジ”になります。
ポイント②:ナレッジを「集約」し「使いやすく」する
ナレッジが属人化する最大の要因の一つが、情報の散在です。
ファイルサーバ、メール、個人のフォルダ…どこに何があるのかわからない、探すのに時間がかかる。それだけで、現場のストレスも、品質リスクも大きくなります。
そこで重要なのが、ナレッジの集約と再整理です。過去に作られた仕様書、マニュアル、FAQ、対応履歴などを、ひとつの仕組みにまとめ直すことで、現場の誰もが“使える情報”になります。
取り組み例:
● 過去の資料を収集し、カテゴリ別に整理し直す
● ファイルサーバの構造を、利用者視点で再編成する
● 「これは使える!」と思えるナレッジをピックアップして共有する文化を作る
「全部整理するのは無理」と感じるかもしれませんが、部分的な見える化でも現場は一気に変わります。たとえば、「〇〇製品の保守FAQだけまとめてみる」でも十分です。
ポイント③:教育体制を「人」から「仕組み」に変える
属人化が進んだ組織では、教育・引継ぎも“人頼み”になりがちです。
「先輩が付きっきりで教える」 「OJTで慣れてもらう」
──たしかに、この方法は効果的な面もあります。しかし、教える側の負担が大きく、新人が担当者の判断を“なんとなく”で覚えることで、ナレッジの再属人化が起こるリスクもあります。
そこで今求められるのは、「誰でも再現可能な教育の仕組み」です。
取り組み例:
● 製品別・課題別のFAQを整備し、自己学習できる仕組みを用意
● サポートに関する「シナリオベースの演習問題」を準備
● 定期的なナレッジ勉強会や、ナレッジ貢献者への表彰制度
教育を「仕組み化」することで、ベテランの知見がチーム全体に広がり、“人に頼らない組織的な成長”が可能になります。
属人化対策は“ムリなく、続ける”がコツ
ここまでご紹介した3つのポイント、
① 業務フローの標準化と可視化
② ナレッジの集約と再整理
③ 教育体制の仕組み化
は、どれもすぐに完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、「できるところから、小さく始めて、習慣化すること」です。
例えば──
●「最近対応した問い合わせを、TIPSとしてSlackに毎週1件共有する」
●「よく聞かれる質問を、FAQスプレッドシートに1件ずつ追加していく」
そんな小さな取り組みでも、“属人化の壁”は少しずつ崩れていきます。
次回予告:ナレッジ×AIで変わるサポートの未来
さて、ここまでの2回で「属人化の問題点」と「脱却のためのポイント」を整理してきました。
第3回ではいよいよ、これらの取り組みを飛躍的に加速させる鍵「AI活用」について解説します。
● 散在ナレッジの自動収集
● マニュアルやFAQの自動生成
● チャットによる即時検索と回答
これまで“人が頑張るしかなかった”属人化対策を、「仕組み+AI」でどう変えていけるのか?
次回もぜひご期待ください。
第3回:ナレッジ×AIで属人化を解消する3つのステップ
属人化を解消するための実践ガイドは以下よりダウンロードいただけます。
