第2回:聞けばわかるWebを、どう実現する?WebRAG型AIチャット導入のステップと活用法
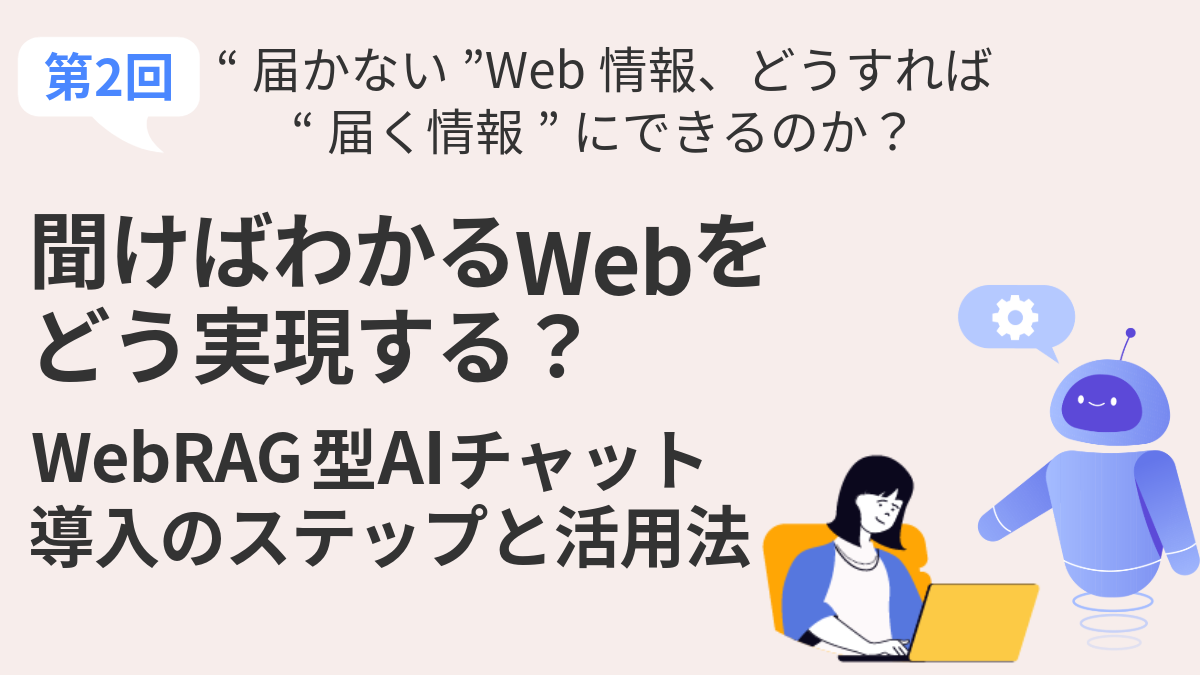
「導入が大変なのでは?」
WebRAG型AIチャットをご紹介する際に、よく聞かれる質問です。
FAQの整備やチャットボットの導入には、構築・保守の手間がどうしてもつきもの。
「便利そうだけど、導入のための作業量が見えないと怖い」――この感覚、よくわかります。
実はWebRAG型AIチャットボットは、そんな心配とは無縁の仕組みです。
今回は、どのように始められるのか、そしてどんな業務で活用されているのかをご紹介します。
前回の記事はこちら
WebRAG型AIチャットの仕組み:どう“検索し、答える”のか?
WebRAG型の「RAG」とは、Retrieval-Augmented Generationの略で、「検索(Retrieval)」と「生成(Generation)」を組み合わせたAIの仕組みです。
たとえばユーザーが「製品Aの初期設定方法を教えて」と質問したとき、AIは以下のような流れで動きます:
Step1:Webから“根拠”を検索(Retrieval)
まず、AIは質問の意図を理解し、企業のWebサイト内にあるHTMLやPDFの中から「関連しそうな情報」を複数ピックアップします。
対象は製品マニュアル、FAQ、サポートページ、IR情報、CSR資料など、サイト全体が情報源になります。
Step2:AIが“自然な答え”を生成(Generation)
次に、検索で得られた複数の根拠をもとに、AIが「人間にとってわかりやすい」自然な文章で回答を生成。
ただ抜き出すだけでなく、質問の文脈に応じて要約・言い換えし、出典URL付きで返してくれます。
Step3:AIに「教え込む作業」がいらない
WebRAG型は、Webが常に情報源です。Webサイトに新しい情報を追加すれば、AIはそれを自動で読み取り、次回以降の回答にすぐ反映します。
従来のチャットボットで必要だったような、「新しい質問を登録する」「回答パターンを追加する」といった人手による学習や調整作業は必要ありません。
AIに“教え込む”ことを前提としなくても、Webにある情報がそのまま回答の材料になるのです。
導入ステップ:必要なのはURLだけ
WebRAG型AIチャットは、導入の簡単さも大きな特徴です。
実際の初期導入ステップは以下の通りです:
1.対象となるWebサイトのURLを指定
2.自動クローリングとインデックス構築(HTML/PDFを含む)
3. 簡易なフィルター設定(除外ページ、非公開エリアなど)
4. チャットUIの埋め込み or URLでの外部提供
サーバー側の特別なセットアップや、FAQの構築作業は不要。
すでに公開されている情報をベースに、短期間でサービス開始が可能です。
「思ったより手間が少ない」と驚かれることも多く、1〜2週間で試験導入まで完了するケースもあります。
運用の負担も“ほぼゼロ”に近い
導入後も、RAG型ならではの特徴で運用の負担はごくわずかです:
● サイト更新があれば定期クローリングで自動反映
● 新しいPDFファイルも都度収集・解析対象に
● 回答の“原文URL”が必ず付くため、問い合わせ側でも確認しやすい
● 誤回答リスクは「出典の検索」段階で大幅に抑制
従来のチャットボットで必要だったスクリプト更新やQ&A登録作業は不要です。
情報の“原本”が常にWebにあるという前提だからこそ、メンテナンスフリーに近い運用が実現します。
活用シーン:社外・社内の情報活用を変える
製造業
・製品仕様・操作手順の即時回答
・型番別マニュアルPDFの案内
・営業チームが自社サイトから即座に資料を取得
自治体
・防災・手続き・ごみ収集など住民質問の即答
・Webに点在するPDF情報を横断的に利用
金融・保険
・契約手続きや申込条件の確認に
・コールセンターの自己解決率向上
教育・医療機関
・膨大な学内資料・手続き案内を集約
・入試/診療/研究内容など多目的に応答
また、社内ヘルプデスクとしても有効です。
就業規則や勤怠ルール、社内システムの使い方といった“散在しやすい社内ナレッジ”を集約・即答できるため、新人対応や情報共有の質が格段に向上します。
まとめ:「現場で“使えるAI”」を、手間なく始める
AIを業務に取り入れたい。
でも、新しいものを導入すると、時間も人手もかかってしまう――
そんなジレンマを解消するのが、このWebRAG型AIチャットです。
すでにWebにある情報を使って、手間なく“届く情報”に変えていく。
社外にも社内にも、問い合わせ前に自己解決できる体験を提供する。
第3回では、AIチャット活用をより高度にするための「ドリルダウンRAG」のしくみをご紹介します。
RAGをさらに正確に、そして“絞り込んで答える”ための進化形です。お楽しみに。
第3回:似て非なる回答を防ぐ。精度と信頼性を両立する「ドリルダウンRAG」とは?
WebRAG型AIチャットボットの特長をくわしくご紹介した資料は以下よりダウンロードいただけます。
